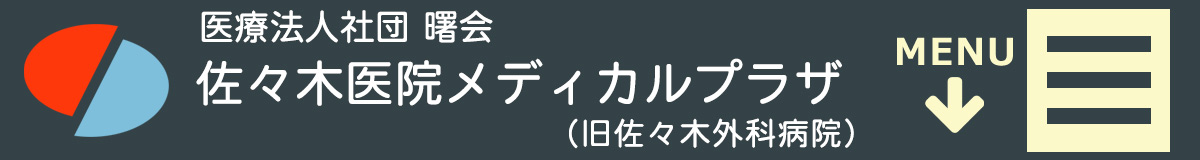スタッフ紹介
内科部長 酒井 勉 内科・消化器
 日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会総合内科専門医日本消化器内視鏡学会専門医
日本化学療法学会抗菌化学療法認定医
日本内科学会認定内科医
麻酔科標榜医
内科 花田 浩 内科・消化器
2025年4月入職日本消化器病学会 専門医・指導医
日本肝臓学会 専門医
日本消化器内視鏡学会 専門医
日本内科学会認定専門医
内科 古賀 博子 内科・消化器
日本内科学会認定医日本消化器病学会専門医
日本肝臓学会専門医
日本医師会認定産業医
内科 鈴木 綾乃 内科・糖尿病
日本内科学会認定医日本内科学会総合内科専門医